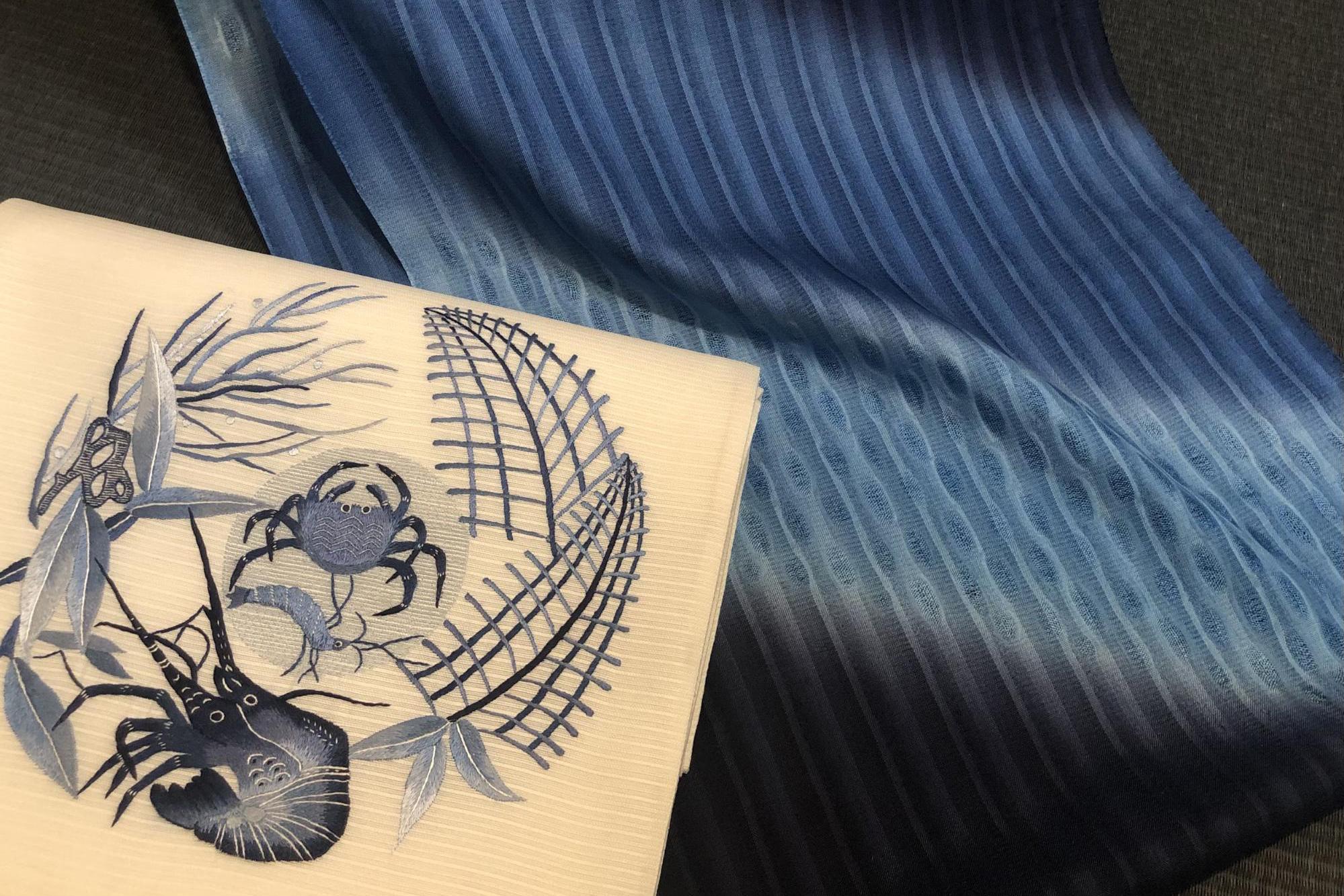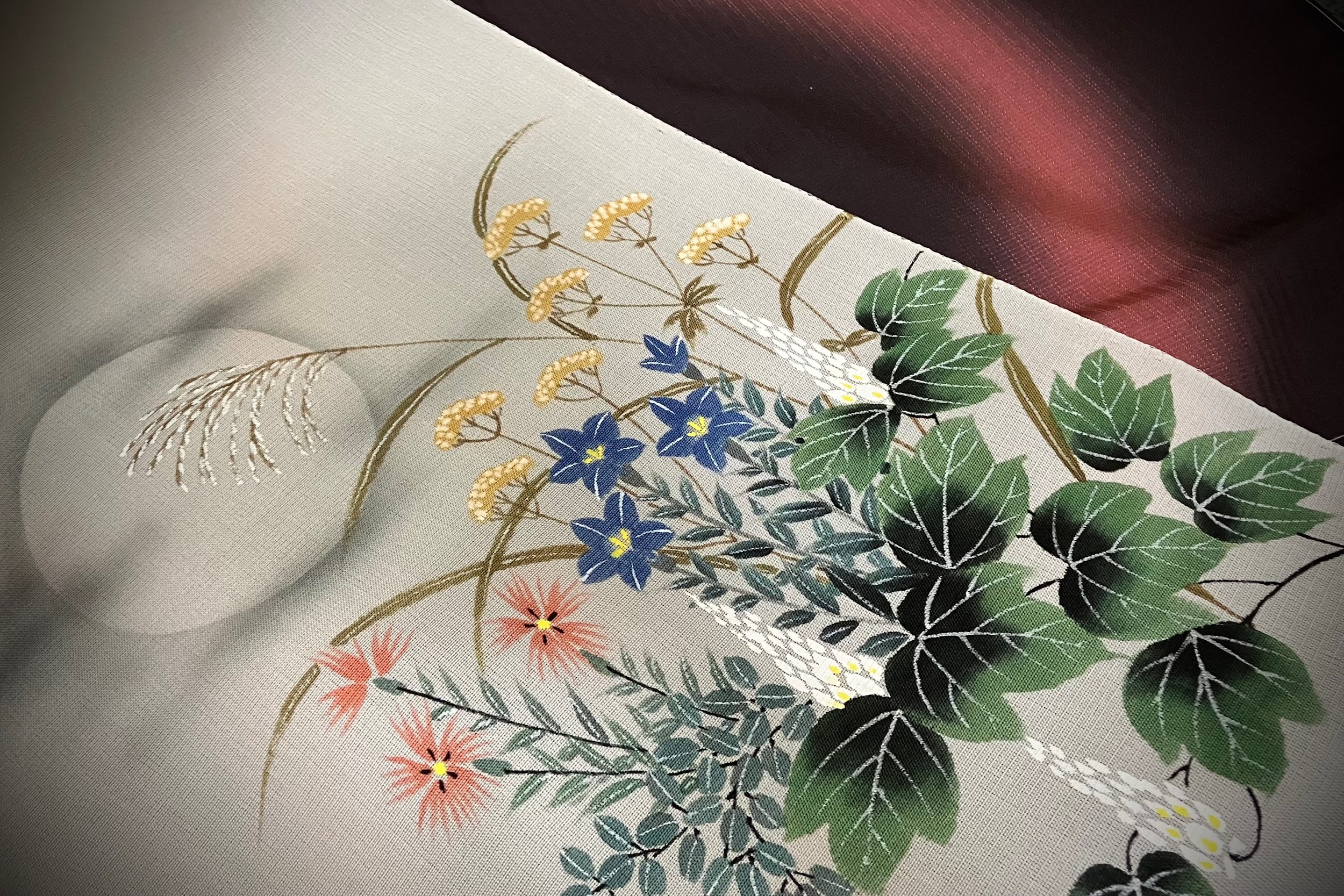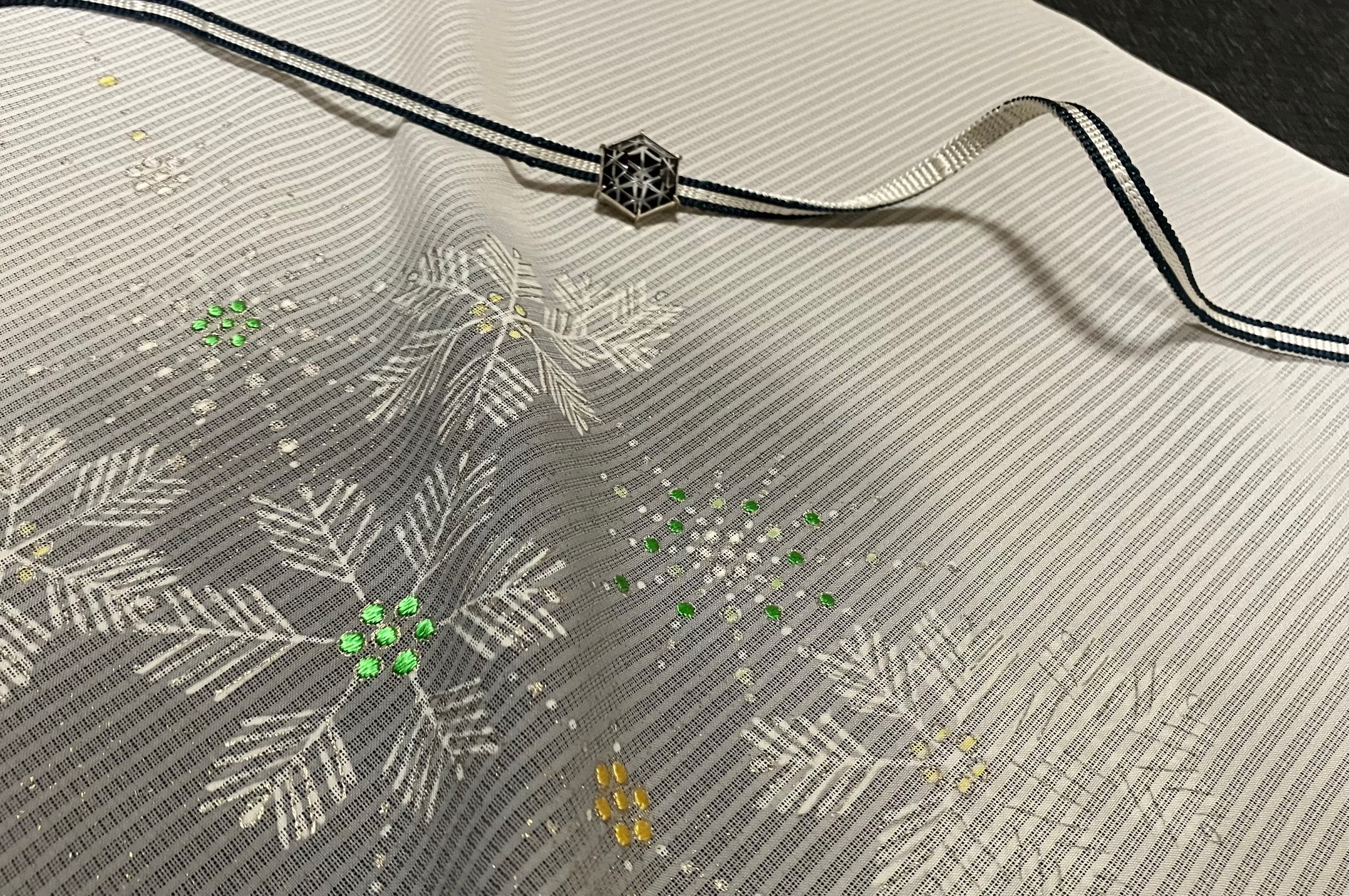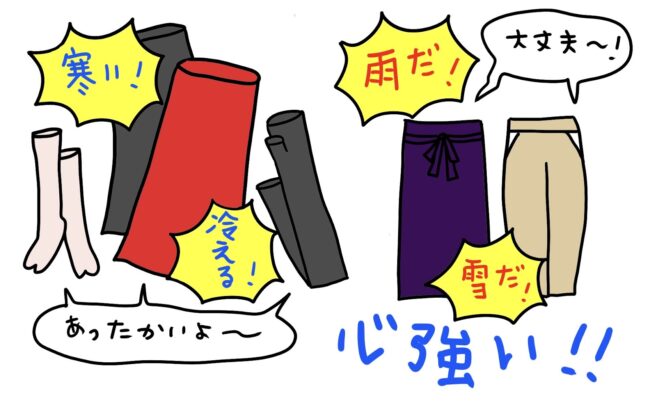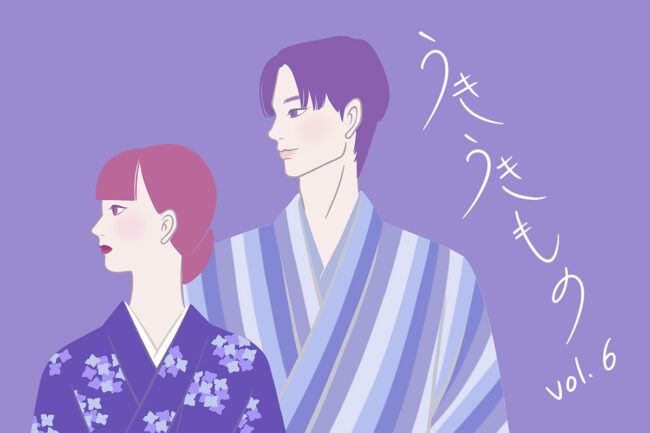生かしきる、ということ 〜小説の中の着物〜 中島要『着物始末暦シリーズ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十六夜
小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は『着物始末暦シリーズ』。「きものは着てこそきもの、着なけりゃただの布きれだ」ー着物の命を生かしきる、そのための“始末”をする。主人公 余一のストレートな言葉が刺さります。
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2025.06.29
連載記事
愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜
-

2025.06.04
連載記事
装いは演出、そして武装〜小説の中の着物〜菊池寛『真珠夫人』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十七夜
-

2025.05.06
連載記事
袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜
-

2025.04.09
連載記事
紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜
-

2024.12.26
連載記事
陽の当たる、その裏で 〜小説の中の着物〜近藤史恵 『散りしかたみに』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十四夜
-

2024.11.28
連載記事
其処ではすべてが露呈する〜小説の中の着物〜 澤田ふじ子『宗旦狐ー茶湯にかかわる十二の短編ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十三夜
-

2024.11.03
連載記事
踊る女と傾く男 〜小説の中の着物〜 天野純希『桃山ビート・トライブ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十二夜
-

2024.10.05
連載記事
憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜
-

2024.09.12
連載記事
誰かのためだけの、ただひとつのもの 〜小説の中の着物〜 知野みさき『神田職人えにし譚』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十夜
-

2024.07.28
連載記事
闇に咲く花 〜小説の中の着物〜 泉ゆたか『髪結百花』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十九夜
-

2024.07.04
連載記事
夏の夜の幻想に酔う 〜小説の中の着物〜 皆川博子『ゆめこ縮緬』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十八夜
-

2024.06.11
連載記事
溺レル幸福 〜小説の中の着物〜 谷崎潤一郎『痴人の愛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十七夜
-

2024.05.14
連載記事
あをによし 〜小説の中の着物〜 永井路子『美貌の女帝』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十六夜
-

2024.04.08
連載記事
日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜
-

2024.03.12
連載記事
節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜
-

2024.02.02
連載記事
美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜
-

2023.12.28
連載記事
徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜
-

2023.12.03
連載記事
働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜
-

2023.11.07
連載記事
“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜
-

2023.10.05
連載記事
掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜
-

2023.08.29
連載記事
愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜
-

2023.07.29
連載記事
雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜
-

2023.07.05
連載記事
羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜
-

2023.06.01
連載記事
宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜
-

2023.04.30
連載記事
女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜
-

2023.03.31
連載記事
蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜
-

2023.03.15
連載記事
滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜
-

2023.02.01
連載記事
“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜
-

2022.12.30
連載記事
“流れる”ような身のこなし 〜小説の中の着物〜 幸田文『流れる』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十夜
-

2022.12.26
連載記事
袖についての、ちょっとした考察 〜小説の中の着物〜 河治和香『国芳一門浮世絵草紙3ー鬼振袖ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十九夜
LATEST最新記事
-

まなぶ
愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

よみもの
憧れの花に「私」を描く。【日本画家 定家亜由子さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.6
-

インタビュー
水川あさみさんが着物ショーに! 和と洋とアートの情熱が融合する『第31回 ファッションカンタータ from KYOTO』
-

よみもの
浴衣を年中、楽しもう。 着物インフルエンサー・さんかくさんの浴衣本『さんかく浴衣のススメ』「きものと編集部の注目アイテム」vol.5
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

よみもの
花街イチのカメラ上手! 宮川町・とし夏菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.1
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

よみもの
世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編
-

よみもの
たくさんの感謝と愛に包まれて。人気芸妓・紗月さん、引き祝いを終えて祇園街を巣立つ
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

よみもの
上七軒の街並みに惹かれ、憧れの舞妓に 上七軒・さと葉さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.19
-

よみもの
是枝裕和監督が描く花街の文化 Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』〈前編〉「きもの de シネマ」番外編
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

よみもの
気品と気さくさが同居する妙 祇園甲部・小扇さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.15
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

よみもの
花街イチのカメラ上手! 宮川町・とし夏菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.1
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

インタビュー
水川あさみさんが着物ショーに! 和と洋とアートの情熱が融合する『第31回 ファッションカンタータ from KYOTO』
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

コラム
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

インタビュー
和姿で登場!深川麻衣さん×室井滋さん独占インタビュー『ぶぶ漬けどうどす』 「きもの de シネマ」番外編
-

まなぶ
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!