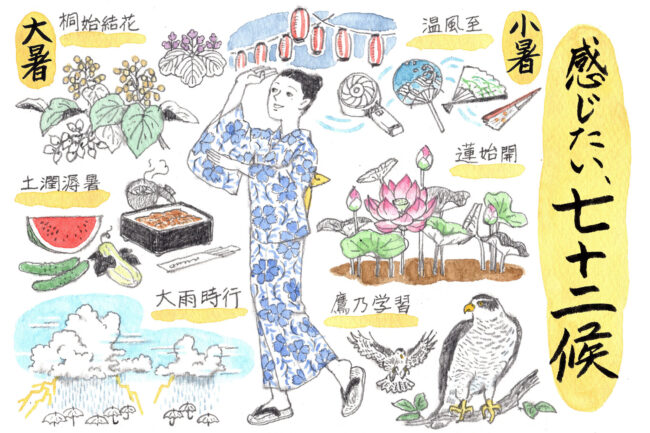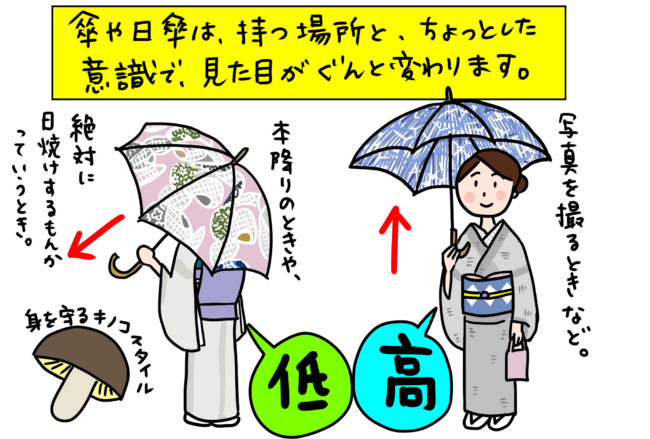浴衣のイメージが覆った”奥州小紋”との出合い 「つむぎみち」 vol.4
『きものが着たくなったなら』(技術評論社)の著者・山崎陽子さんが綴る連載「つむぎみち」。おだやかな日常にある大人の着物のたのしみを、織りのきものが紡ぎ出す豊かなストーリーとともに語ります。
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2025.07.04
連載記事
160亀甲の本場結城紬が誘ってくれた世界 「つむぎみち」 vol.13(最終回)
-

2025.07.04
連載記事
畏れ多いと敬遠していた、郡上紬とのご縁 「つむぎみち」 vol.12
-

2025.07.04
連載記事
優しさと強さと。上田紬の格子のさりげなさ 「つむぎみち」 vol.11
-

2025.07.04
連載記事
紅色と黄色が優しい、紅花染めの置賜紬 「つむぎみち」 vol.10
-

2025.07.04
連載記事
秋単衣は、さらっとした縞大島と軽い八寸帯で始めたい 「つむぎみち」 vol.9
-

2025.07.04
連載記事
洋服感覚で着る”小千谷ちぢみ”の新しい楽しみ 「つむぎみち」 vol.8
-

2025.07.04
連載記事
超絶技巧から生まれる、”長板中形”の清しい白 「つむぎみち」 vol.7
-

2025.07.04
連載記事
一生着ることはないと思っていた、”越後上布”との邂逅。 「つむぎみち」 vol.6
-

2025.07.04
連載記事
“蝉の翅”と称される夏の絹、”明石ちぢみ”の繊細さ 「つむぎみち」 vol.5
-

2025.07.04
連載記事
浴衣のイメージが覆った”奥州小紋”との出合い 「つむぎみち」 vol.4
-

2025.07.04
連載記事
座繰りの玉糸が生む”しょうざん生紬”の素朴 「つむぎみち」 vol.3
-

2025.07.04
連載記事
明るい日差しに映える、黄八丈の”まるまなこ” 「つむぎみち」 vol.2
-

2025.07.04
連載記事
初夏の訪れを肌に伝える、本塩沢ならではのしゃり感 「つむぎみち」 vol.1
LATEST最新記事
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

まなぶ
木綿着物とは?特徴や着こなし方をご紹介
-

まなぶ
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!
-

new着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

まなぶ
浴衣を着よう!大人の女性ならではのカッコいい着こなし術 「大久保信子さんのきもの練習帖」vol.1
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

まなぶ
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!
-

よみもの
常識をアップデート!2WAYで楽しむ浴衣「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」番外編
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

まなぶ
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

new着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味