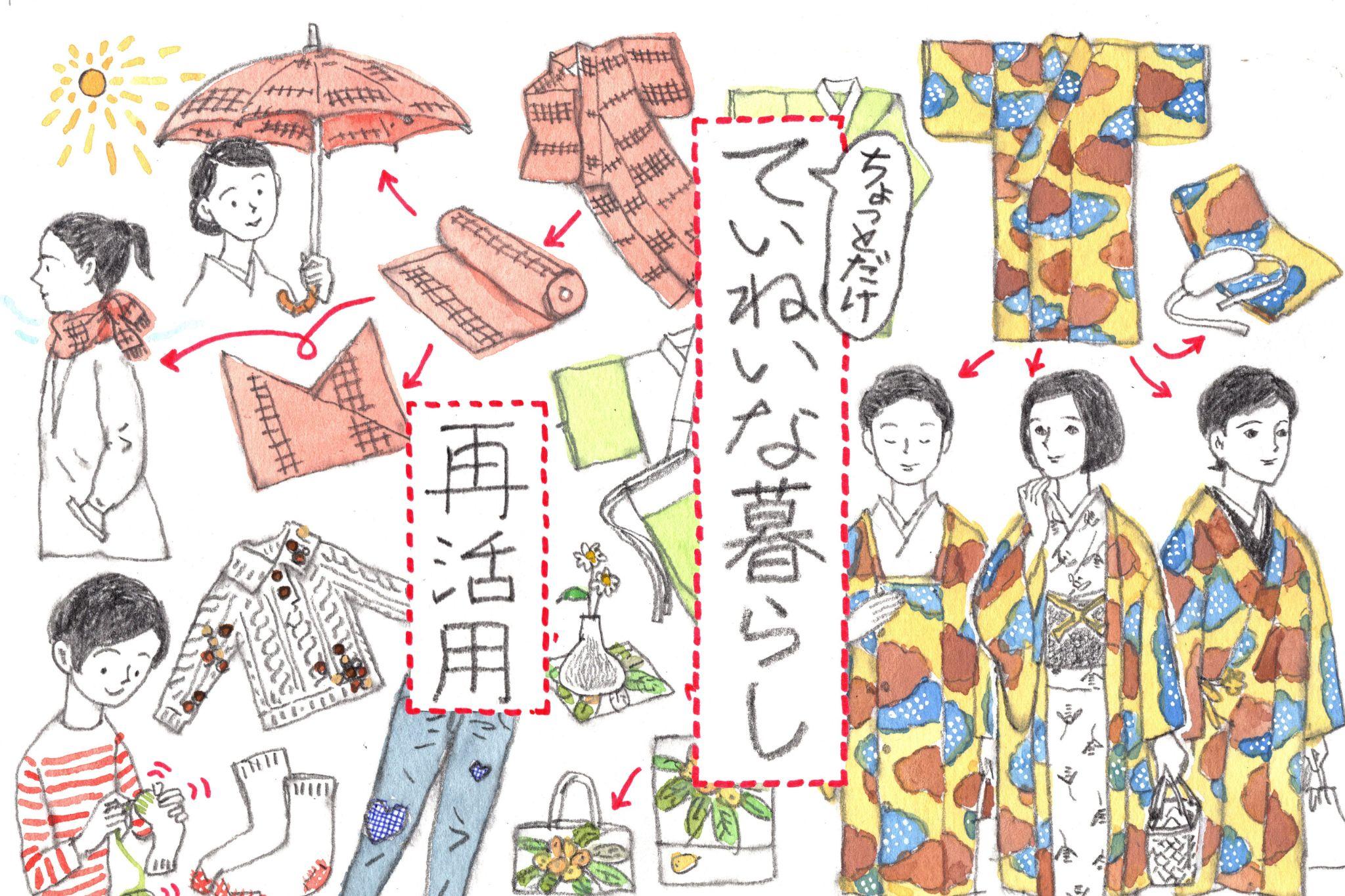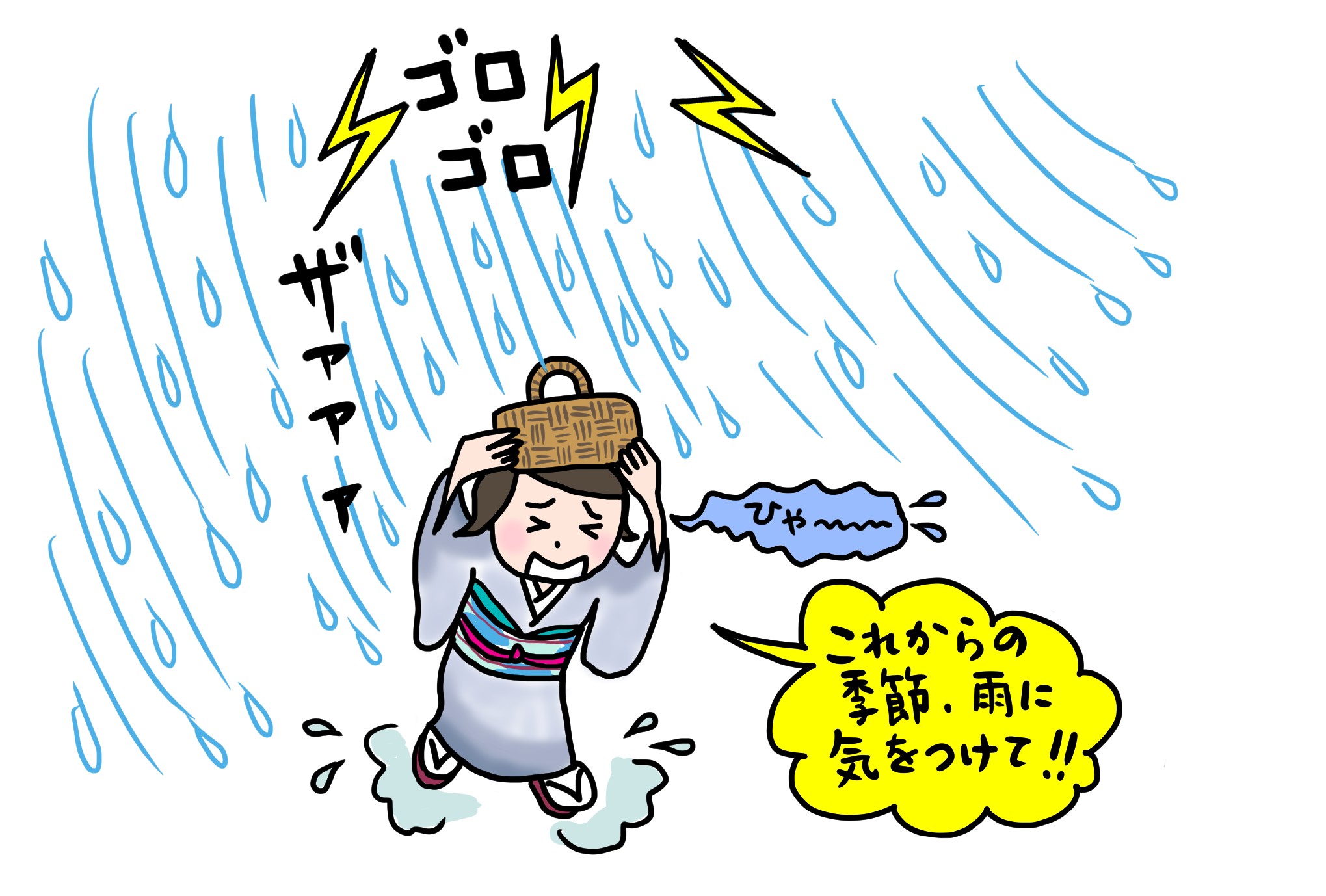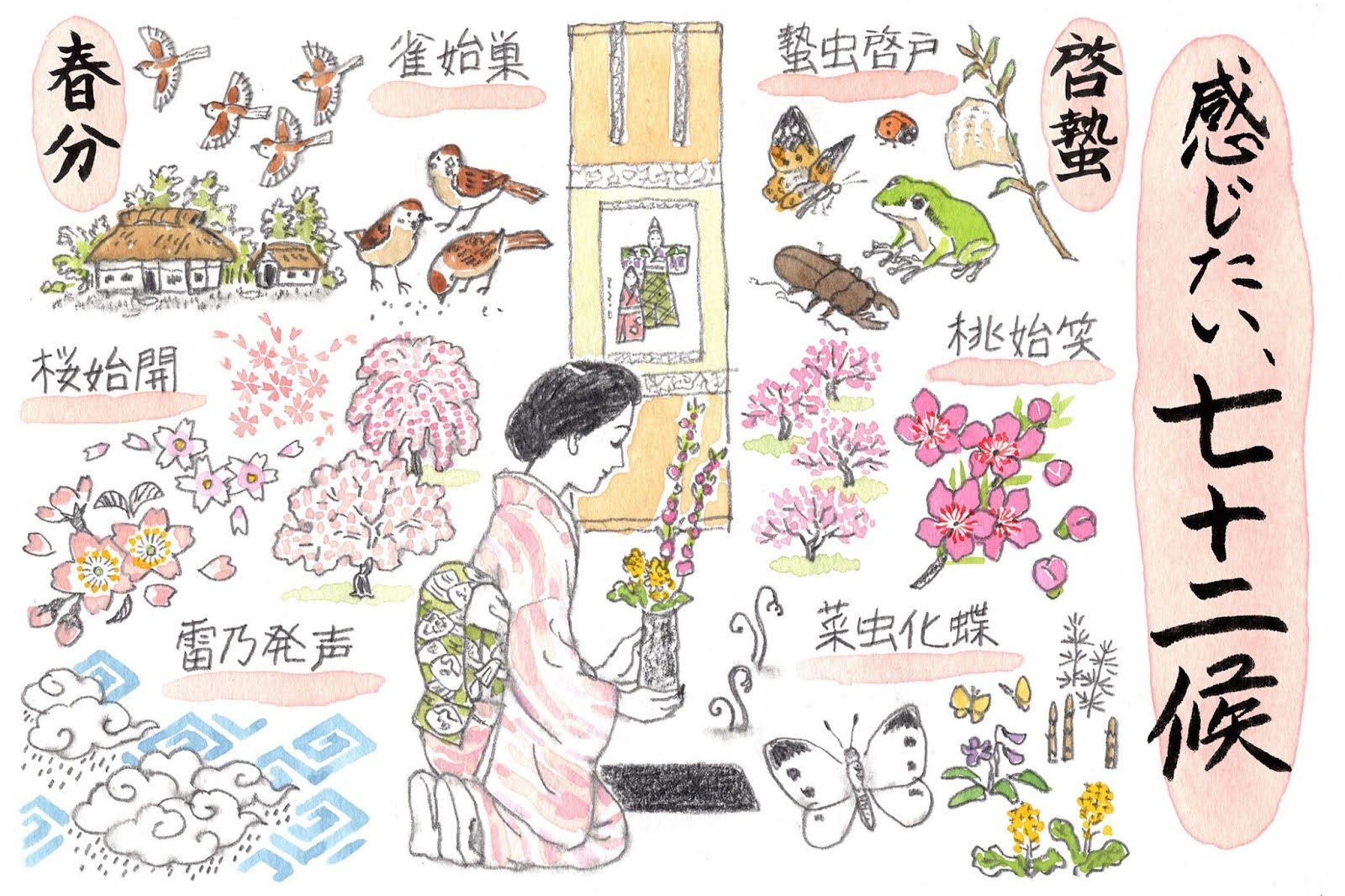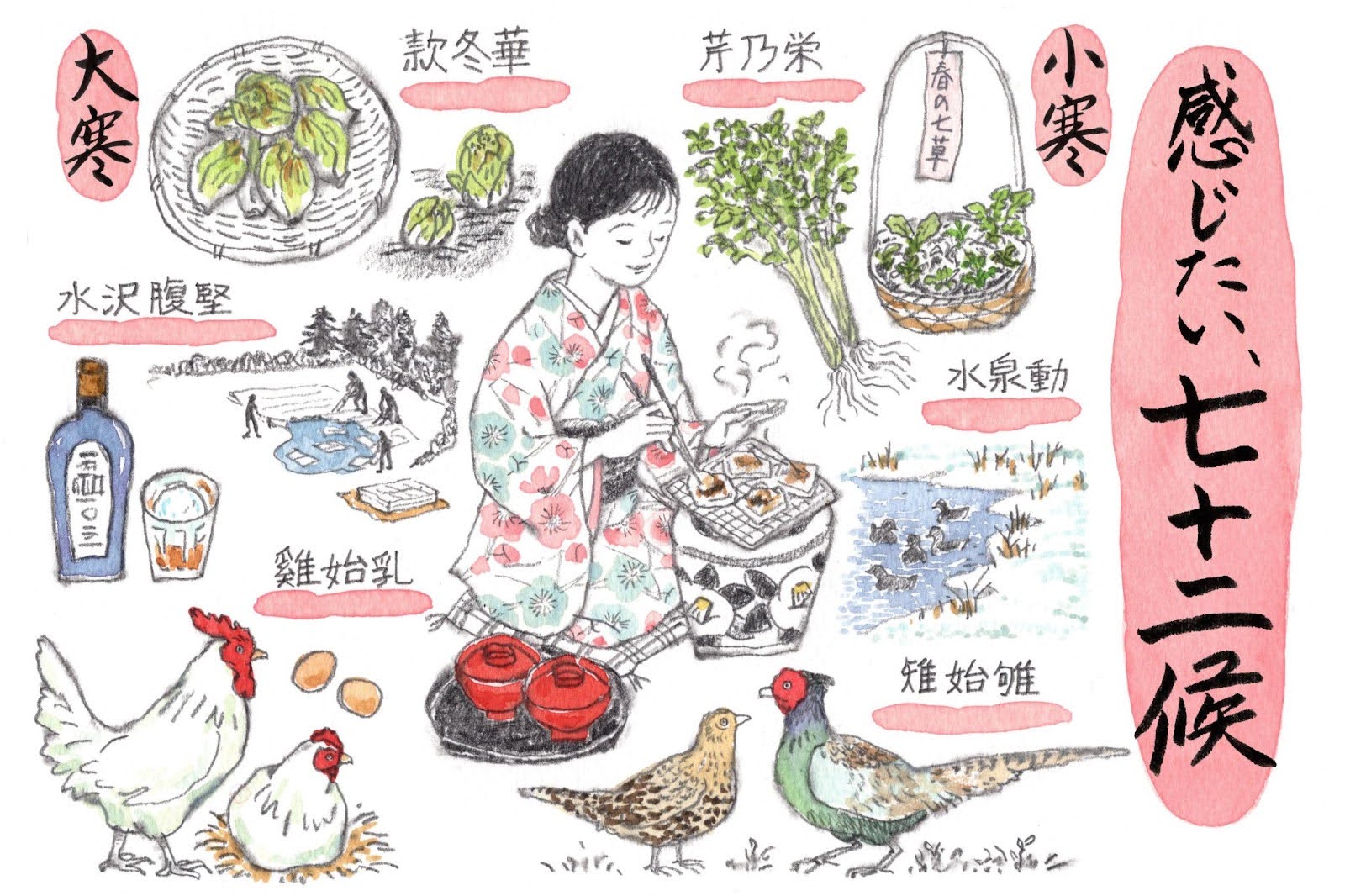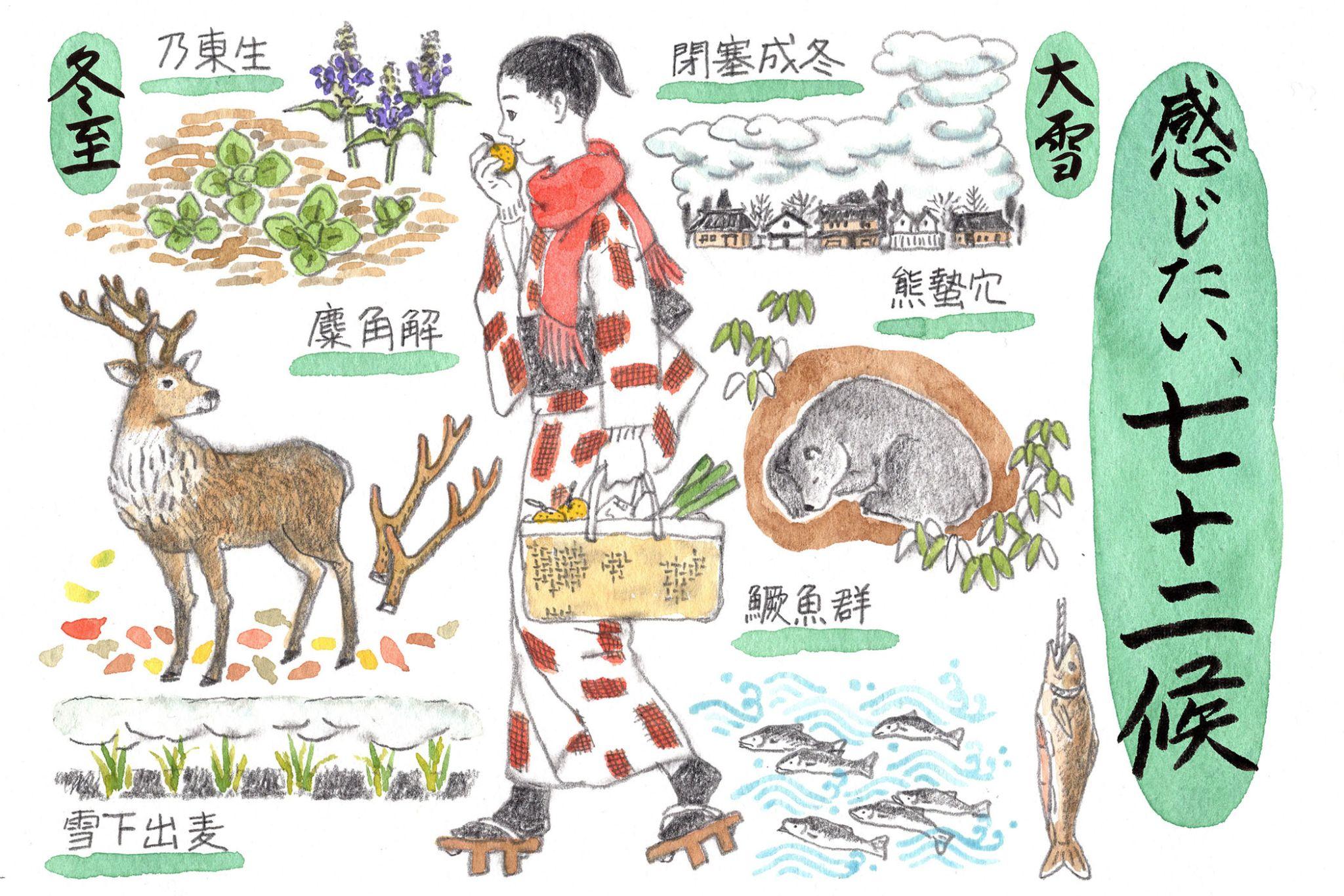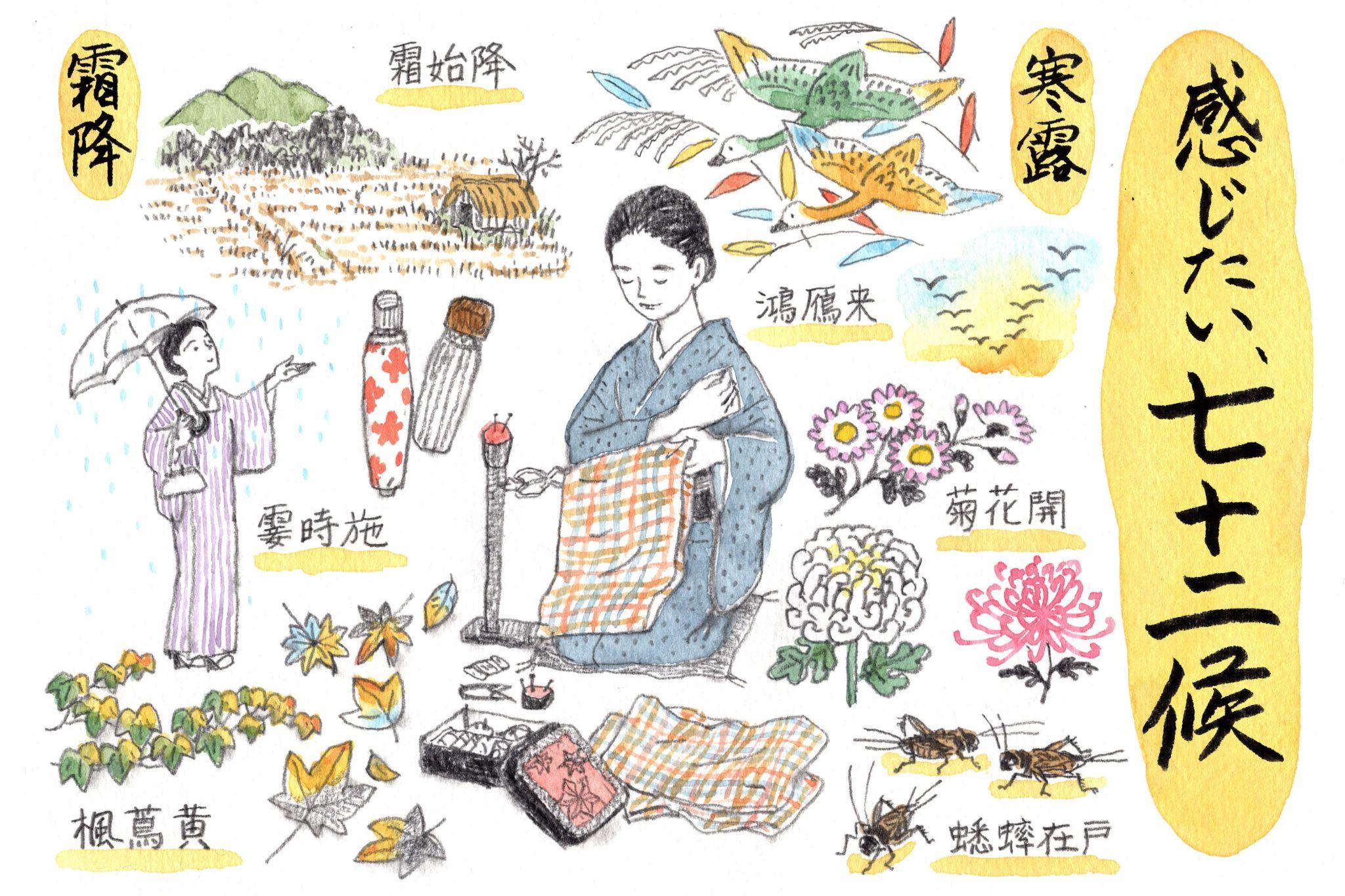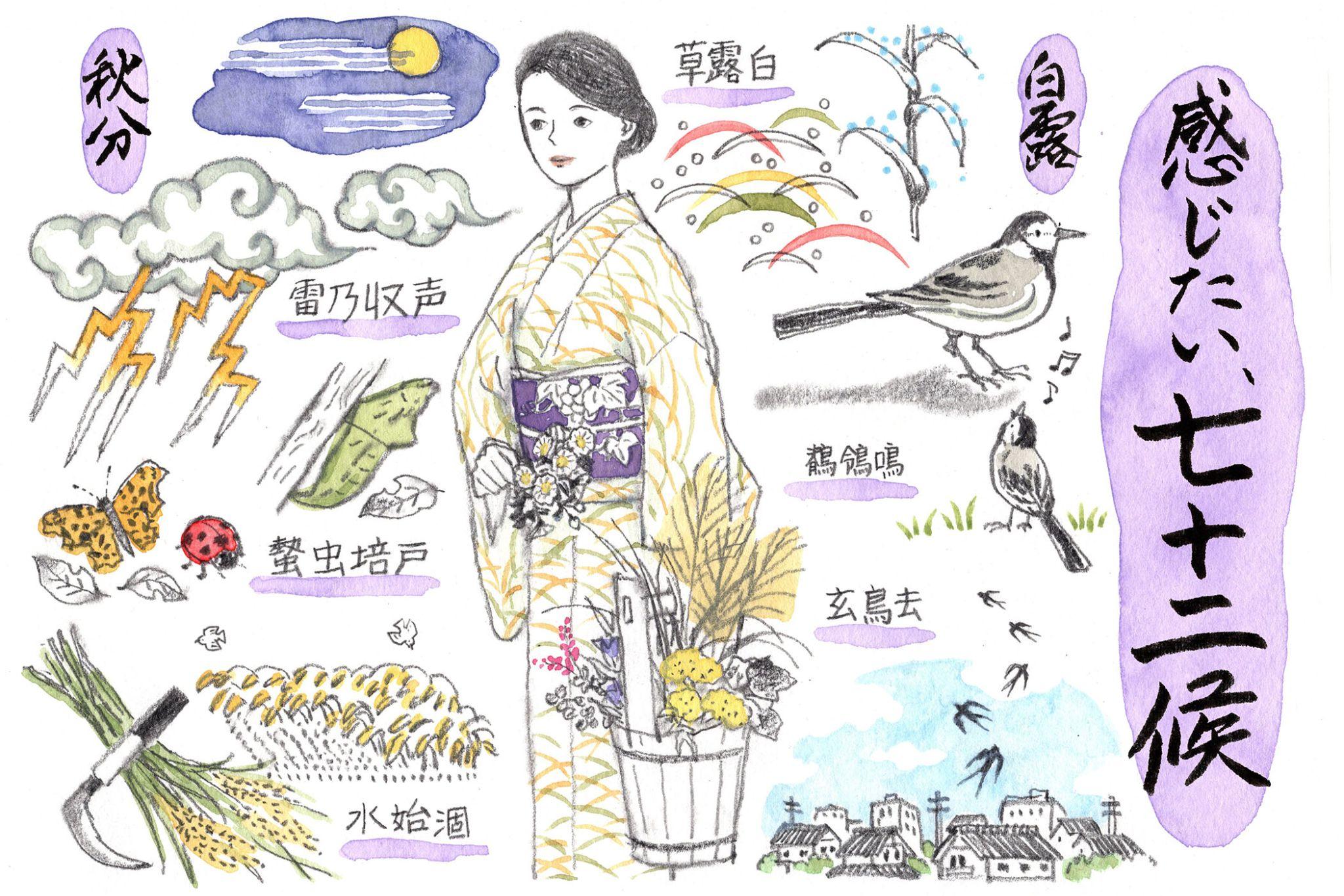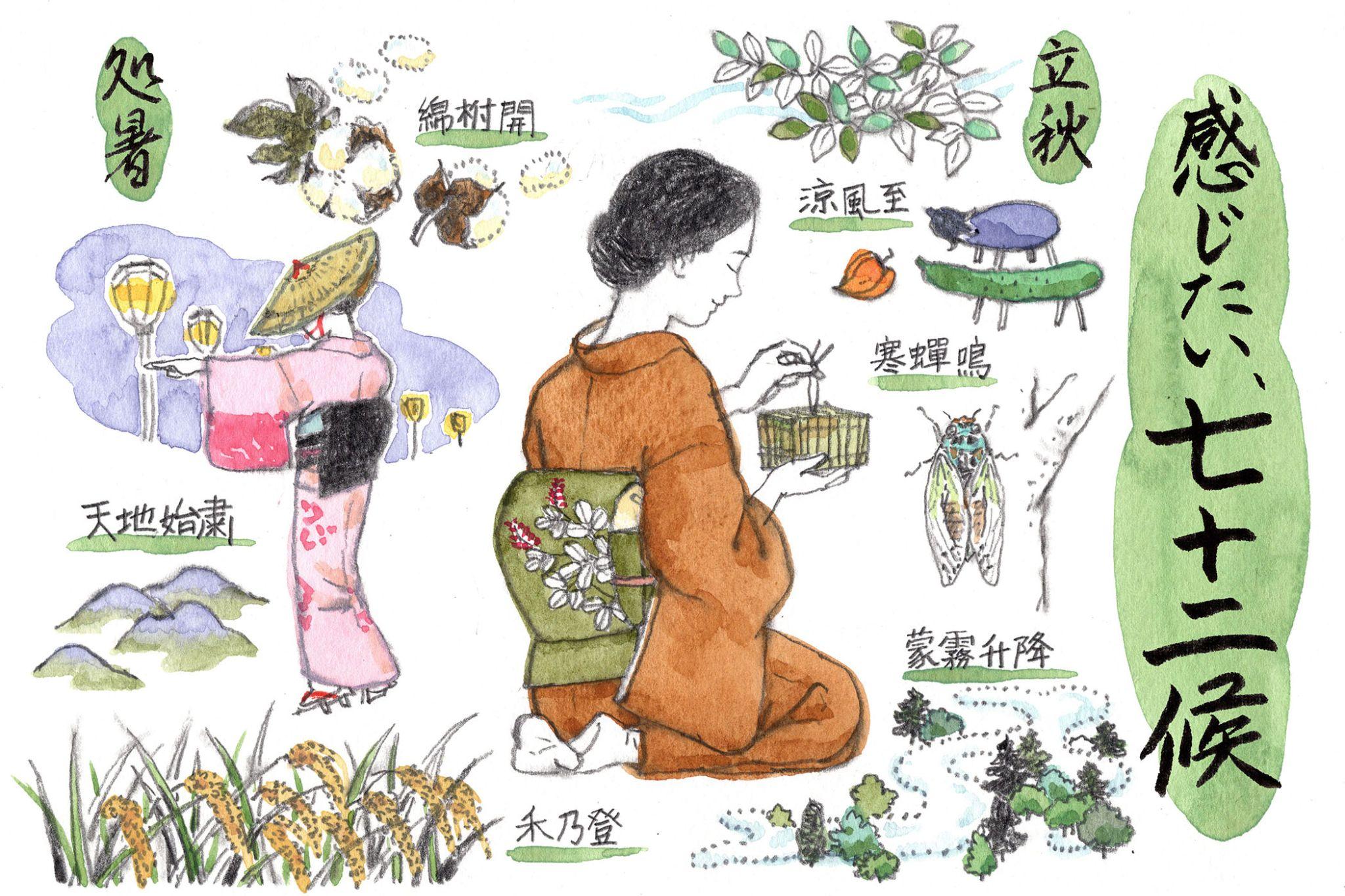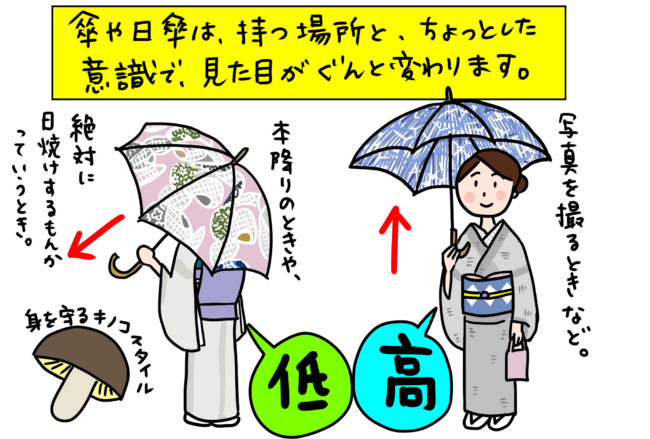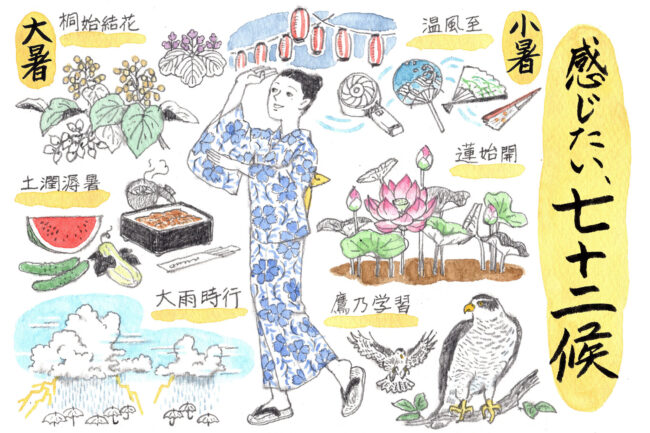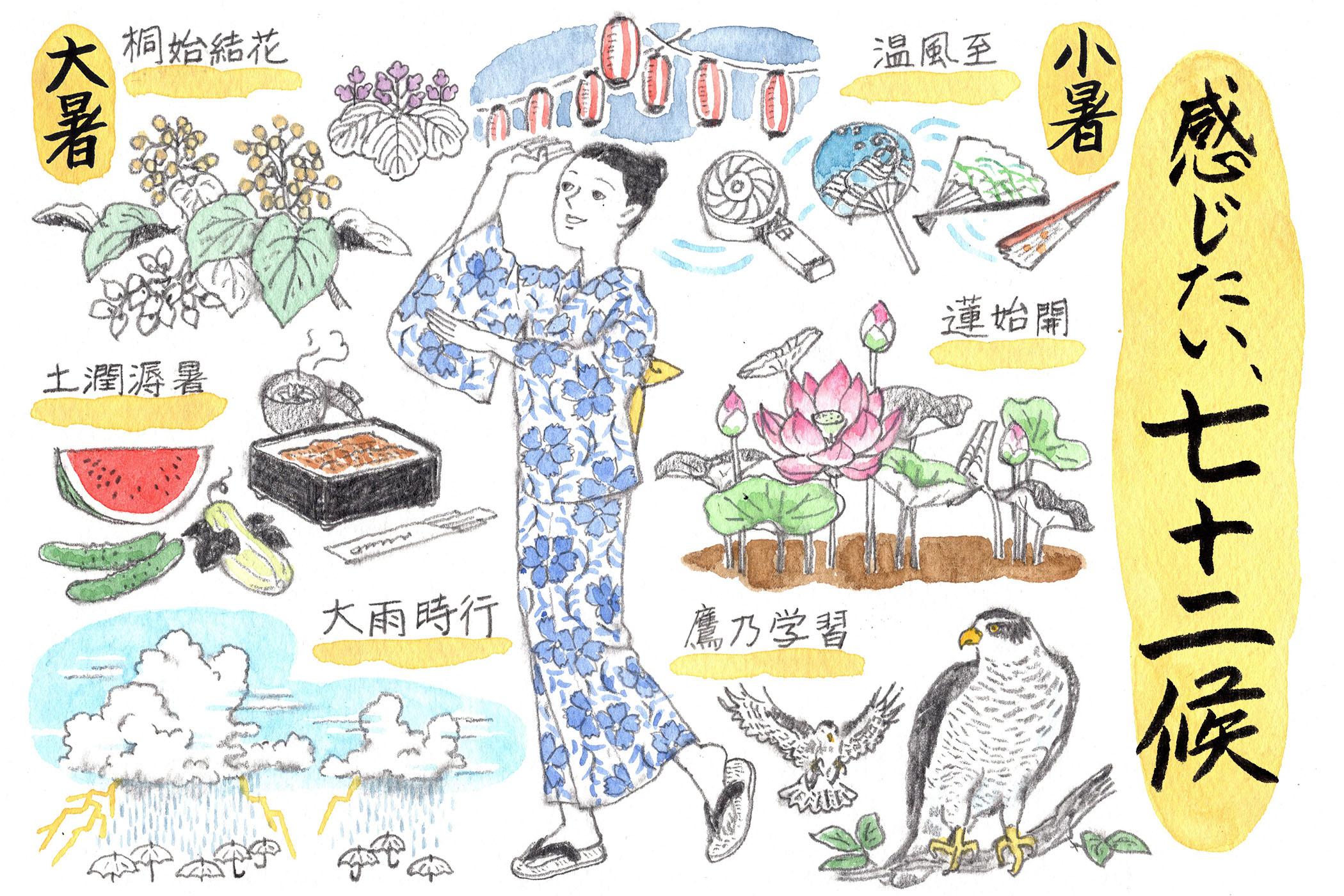
晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)
夏着物も本格的に薄物を楽しめる季節ですね。個人的にこの夏は、持っている浴衣をもっと楽しみたいと思っています。
目次
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2025.07.03
連載記事
晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)
-

2025.06.04
連載記事
仲夏の候 ―芒種から夏至 「感じたい、七十二候」vol.11
-

2025.05.06
連載記事
初夏の候 ―立夏から小満 「感じたい、七十二候」vol.10
-

2025.05.06
連載記事
晩春の候 ―清明から穀雨 「感じたい、七十二候」vol.9
-

2025.05.21
連載記事
仲春の候 ―啓蟄から春分 「感じたい、七十二候」vol.8
-

2025.05.06
連載記事
初春の候 ―立春から雨水 「感じたい、七十二候」vol.7
-

2025.05.06
連載記事
晩冬の候―小寒から大寒「感じたい、七十二候」vol.6
-

2024.12.05
連載記事
仲冬の候 ―大雪から冬至 「感じたい、七十二候」vol.5
-

2024.11.11
連載記事
初冬の候 ―立冬から小雪 「感じたい、七十二候」vol.4
-

2025.05.06
連載記事
晩秋の候 ―寒露から霜降 「感じたい、七十二候」vol.3
-

2025.05.06
連載記事
仲秋の候 ―白露から秋分 「感じたい、七十二候」vol.2
-

2024.08.08
連載記事
初秋の候 ―立秋から処暑 「感じたい、七十二候」vol.1
LATEST最新記事
-

まなぶ
NAMINORI 渡ってみせたい、大海原!「うきうきもの」vol.7
-

よみもの
晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

よみもの
探してみよう!持っていて、うきうきする日傘 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.97
-

まなぶ
愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

コラム
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

よみもの
中村萬太郎夫人 小川絵美子さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.4 ―着物が深めてくれるお客さまとのつながり
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

まなぶ
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

よみもの
花街イチのカメラ上手! 宮川町・とし夏菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.1
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

よみもの
世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

よみもの
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

まなぶ
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

まなぶ
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

インタビュー
自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2
-

インタビュー
美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3
-

まなぶ
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

コラム
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

まなぶ
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!