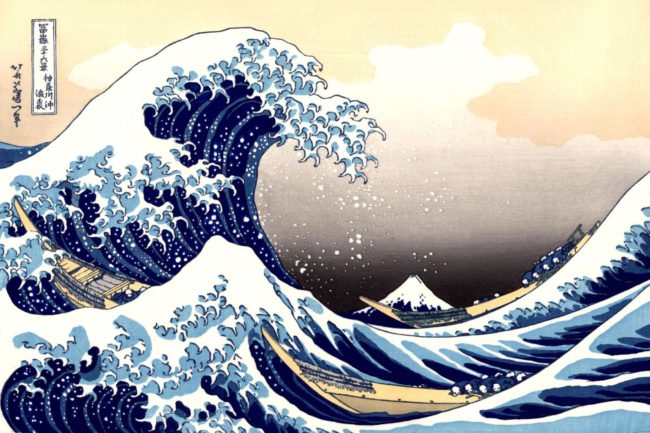【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。
過日、建仁寺塔頭両足院で映像作家・河瀨直美さんと伊藤姉弟との対談が行われました。副住職である伊藤東凌さんからバトンを受け取ったのは、姉の伊藤仁美さん。生まれ育った場所で、念願だった河瀨監督との顔合わせが叶いました。着物家である仁美さんとの対談テーマは、ずばり「着物」。その魅力や文化について、想いの籠った語りが重ねられました。
目次
シェア
RECOMMENDおすすめ記事
Related Posts
LATEST最新記事
-

インタビュー
【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。
-

ライフスタイル
世の中の役に立つ企業をめざして【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決! vol.10
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

ファッション
着物にも通じるジャパニーズ・ジュエラーの実力 『ウエダジュエラー』後編「日本のジュエラーを訪ねて」vol.2
-

カルチャー
葉月、五山送り火に添える彩り 「未生流笹岡家元に学ぶ、華やぎあるくらし」vol.12(最終回)
-

エッセイ
Fun Sunflowers 眩しいくらいの暑さを楽しもう!「うきうきもの」vol.8
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

着物の基本
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

着物の基本
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!
-

着物の基本
まだまだ浴衣! 8月後半の大人浴衣とは!?「着物ひろこの着付けTIPs」vol.8
-

カルチャー
首里織 工房真南風(沖縄県中頭郡読谷村)「バイヤー野瀬の、きもの産地巡り」vol.2
-

エッセイ
半幅帯は4m以上のものを”適当に” 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.57
-

カルチャー
浮世絵はどうやって作られる? 「浮世絵きほんのき!」vol.3
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

着物でおでかけ
特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49
-

カルチャー
終戦80年、長崎に想い馳せる夏『長崎―閃光の影で―』『遠い山なみの光』 「きもの de シネマ」vol.67
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

着物の基本
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

着物の基本
作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

着物の基本
作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!
-

着物の基本
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!
-

着物でおでかけ
特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49