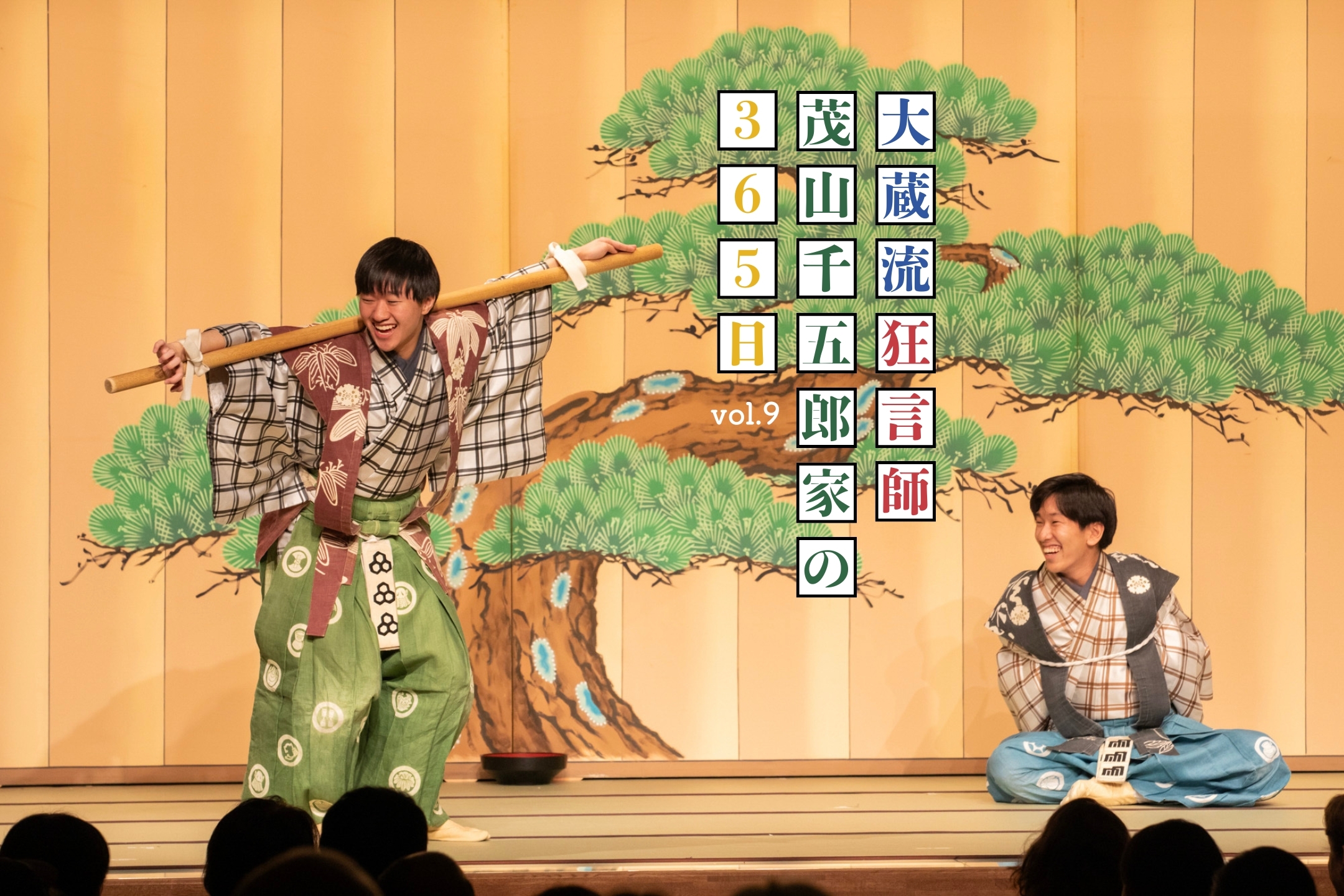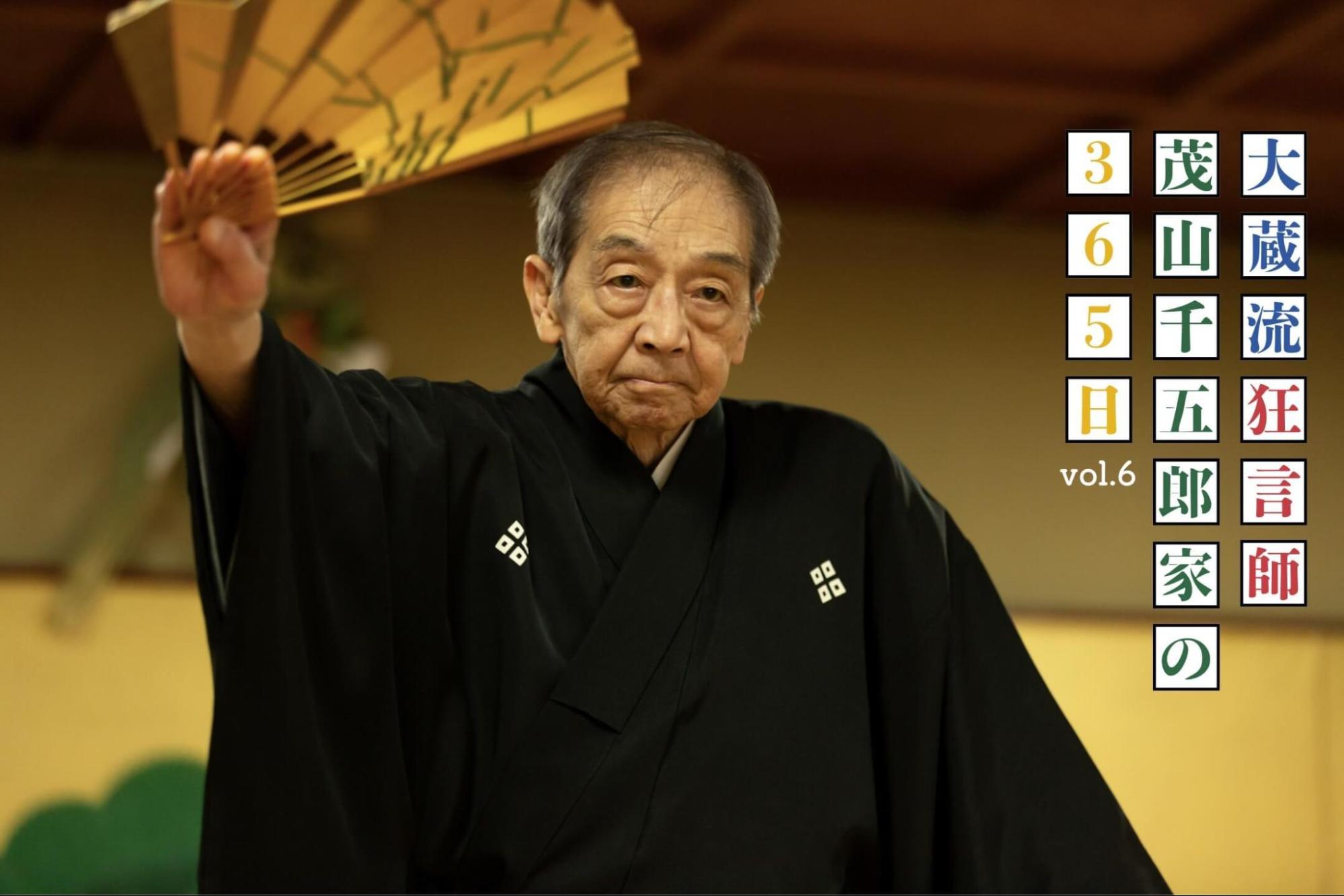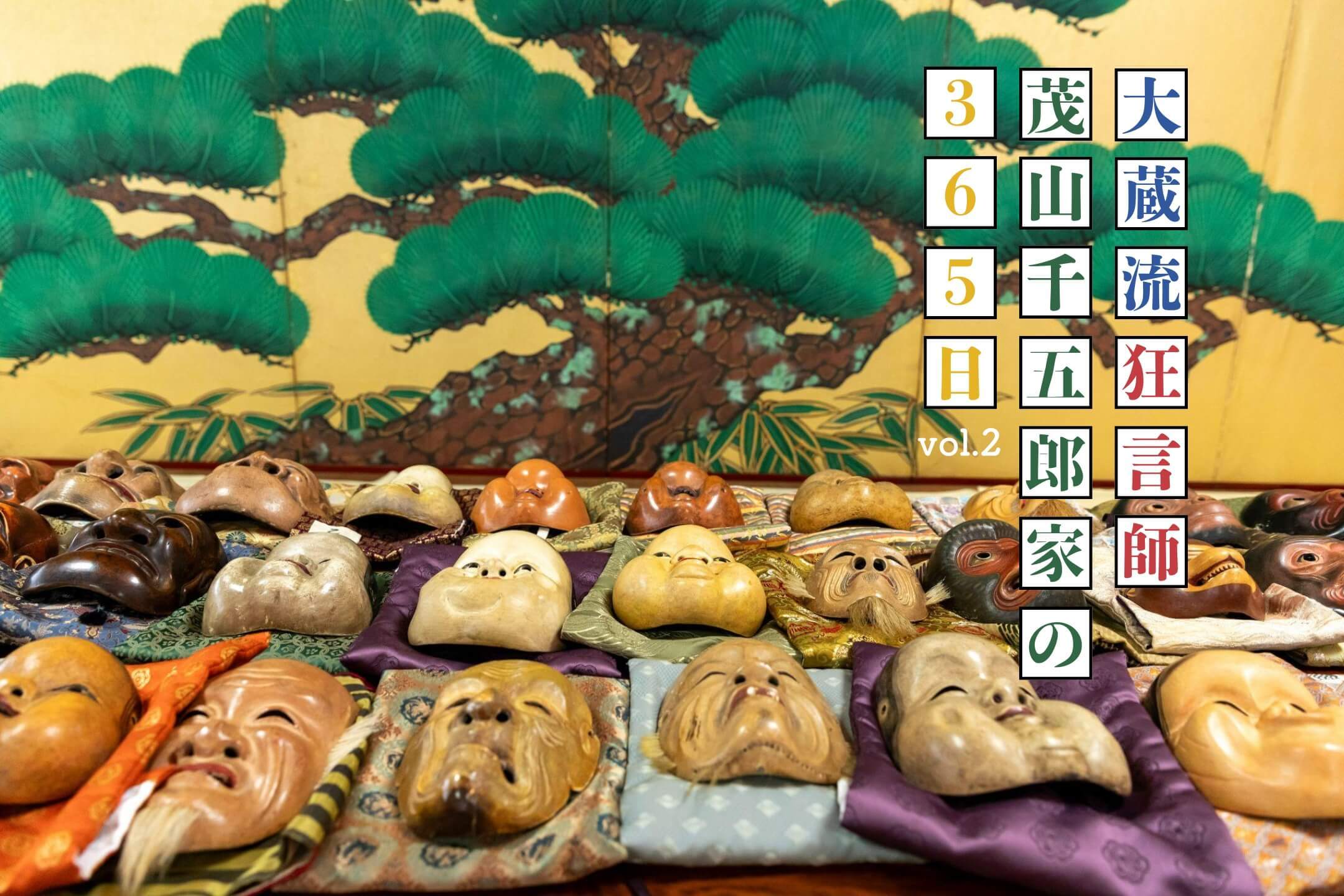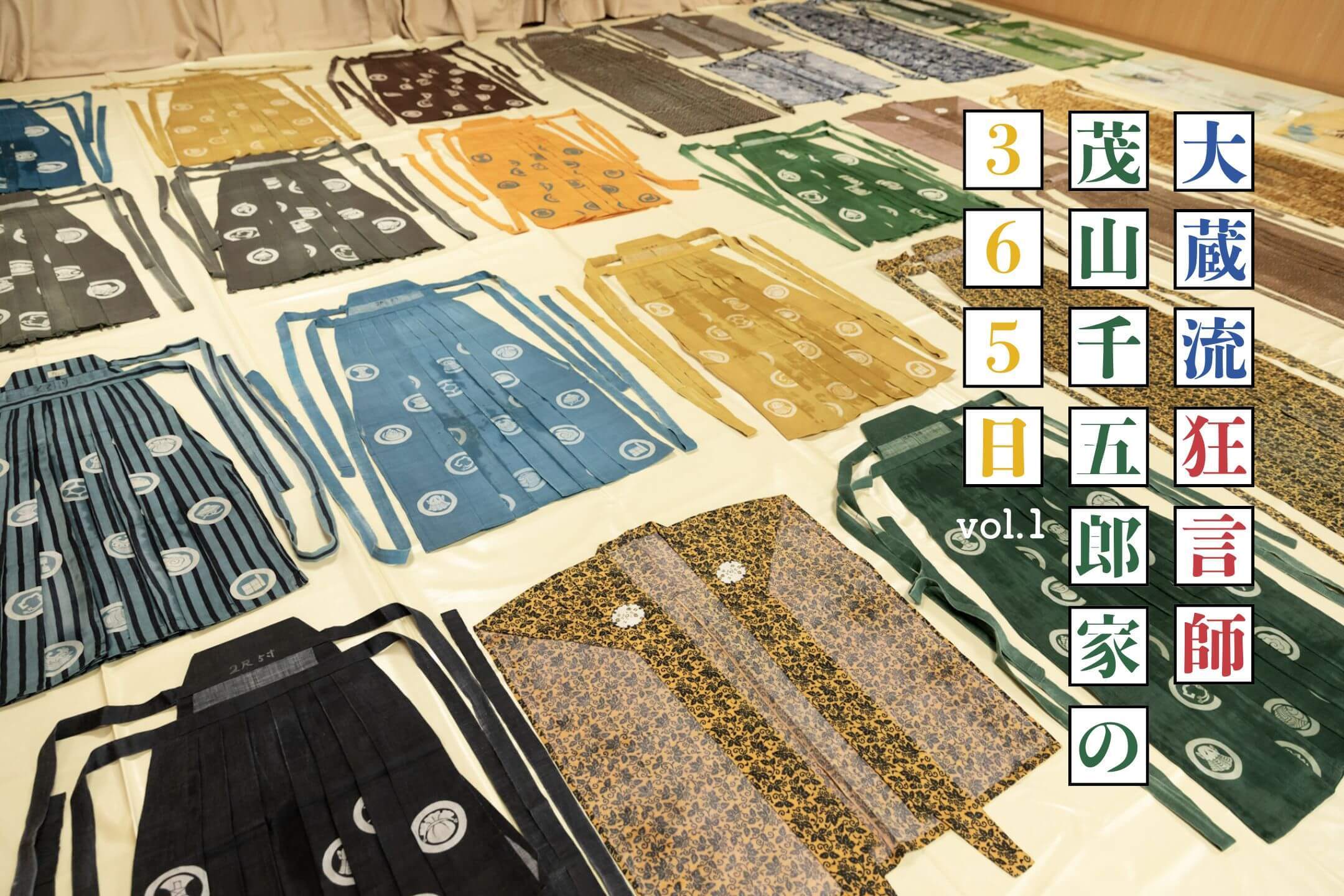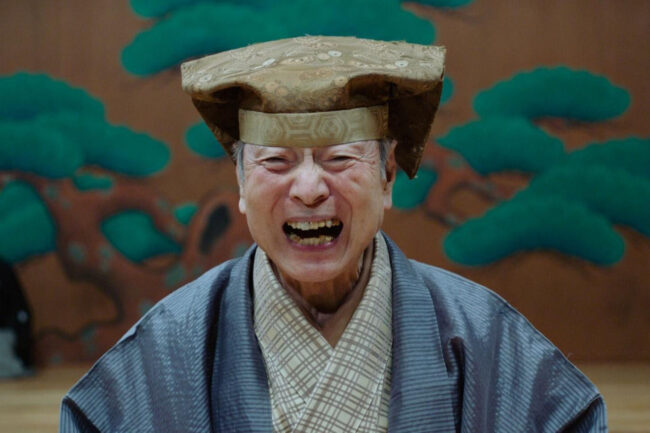茂山千五郎家と祇園祭 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.11(最終回)
室町時代から400年にわたって京都で狂言の普及・継承に勤めている茂山千五郎家の1年間に密着する連載も、いよいよ最終回です。装束の虫干しから始まった当連載の最後となる今回は、日本三大祭のひとつである「祇園祭」と茂山千五郎家の関わりについてご紹介します。
目次
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2025.07.28
連載記事
茂山千五郎家と祇園祭 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.11(最終回)
-

2025.07.28
連載記事
千五郎家所蔵の狂言装束、大解剖! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.10
-

2025.07.28
連載記事
ギオンコーナー、それは伝統への玄関口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.9
-

2025.07.28
連載記事
千五郎家の若奥様好みを大公開! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」番外編
-

2025.07.28
連載記事
千五郎家における縁の下の山の神 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.8
-

2025.07.07
連載記事
福はうち~!良き鬼からの厄除け豆 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.7
-

2025.07.07
連載記事
初春を寿ぐ儀式「舞初式」に密着 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.6
-

2025.07.07
連載記事
新作公演が広げる、狂言への間口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.5
-

2025.07.07
連載記事
狂言を習い事に? 茂山千五郎家の社中とは 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.4
-

2025.07.07
連載記事
歴史ある『茂山狂言会』に託す想い 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.3
-

2025.07.07
連載記事
佳景かな!狂言面の虫干し 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.2
-

2025.07.07
連載記事
壮観なり!狂言装束の糊付け 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.1
LATEST最新記事
-

ライフスタイル
着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8
-

カルチャー
遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2
-

ライフスタイル
【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1
-

カルチャー
人間国宝・野村万作氏の狂言に捧げた90年『六つの顔』 「きもの de シネマ」vol.68
-

インタビュー
【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。
-

ライフスタイル
世の中の役に立つ企業をめざして【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決! vol.10
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

ライフスタイル
桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

カルチャー
遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

ライフスタイル
端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

ライフスタイル
桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

ライフスタイル
端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

ライフスタイル
萬燈会とお盆飾り 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.8
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

着物の基本
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

着物の基本
浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!