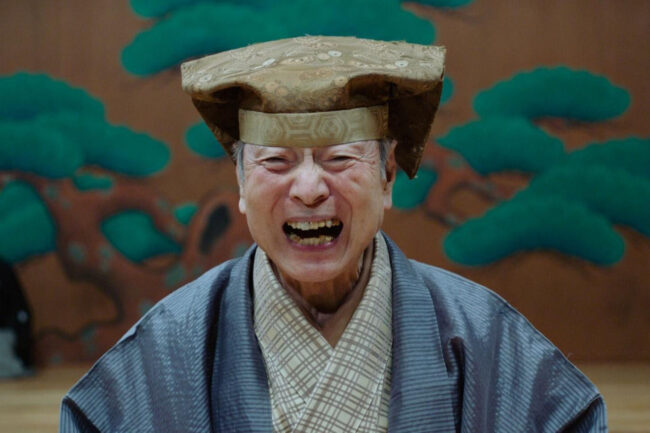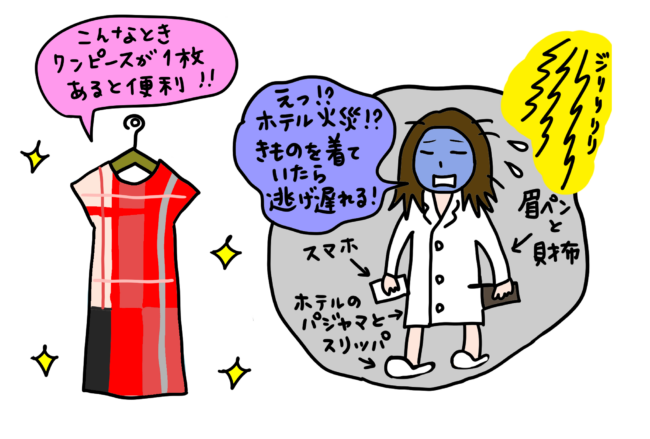祇園甲部の芸妓・舞妓が華やかに舞う、『都をどり』の魅力に迫る!
京の春の風物詩『都をどり』が始まりました。約50名の祇園甲部芸妓・舞妓らが京都の名所を背景に舞う「都風情四季彩」の歴史と見どころをご紹介します。
シェア
RECOMMENDおすすめ記事
Related Posts
LATEST最新記事
-

イベント
大阪・関西万博で花魁パフォーマンス! 「Magnificent KIMONO!」vol.15(最終回)
-

インタビュー
妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編
-

インタビュー
【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション
-

ライフスタイル
褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3
-

エッセイ
small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9
-

カルチャー
戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物でおでかけ
特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49
-

イベント
大阪・関西万博で花魁パフォーマンス! 「Magnificent KIMONO!」vol.15(最終回)
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

ライフスタイル
着物の新しい形、守るべき伝統 「WORLD KIMONO SNAPS」 ‐ NEW YORK ‐
-

コラム
初心者でも可能?着物の着方・着付けの手順を写真で解説!
-

エッセイ
浴衣を着よう!大人の女性ならではのカッコいい着こなし術 「大久保信子さんのきもの練習帖」vol.1
-

カルチャー
その愛嬌こそが愛される所以 祇園東・雛佑さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.10
-

エッセイ
small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9
-

イベント
『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14
-

エッセイ
9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

着物の基本
着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!
-

インタビュー
妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編
-

インタビュー
色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

エッセイ
9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

エッセイ
きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99
-

イベント
『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!