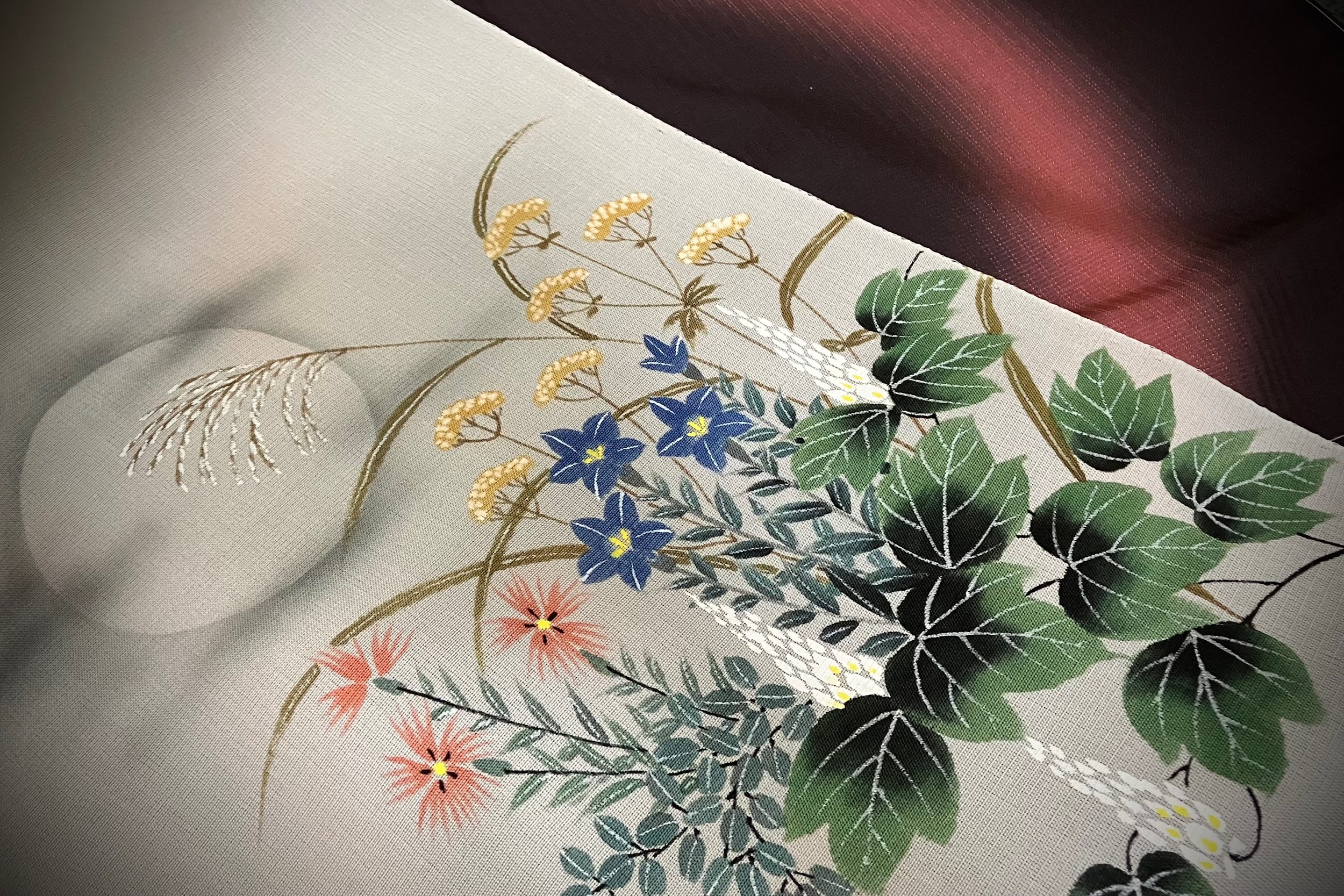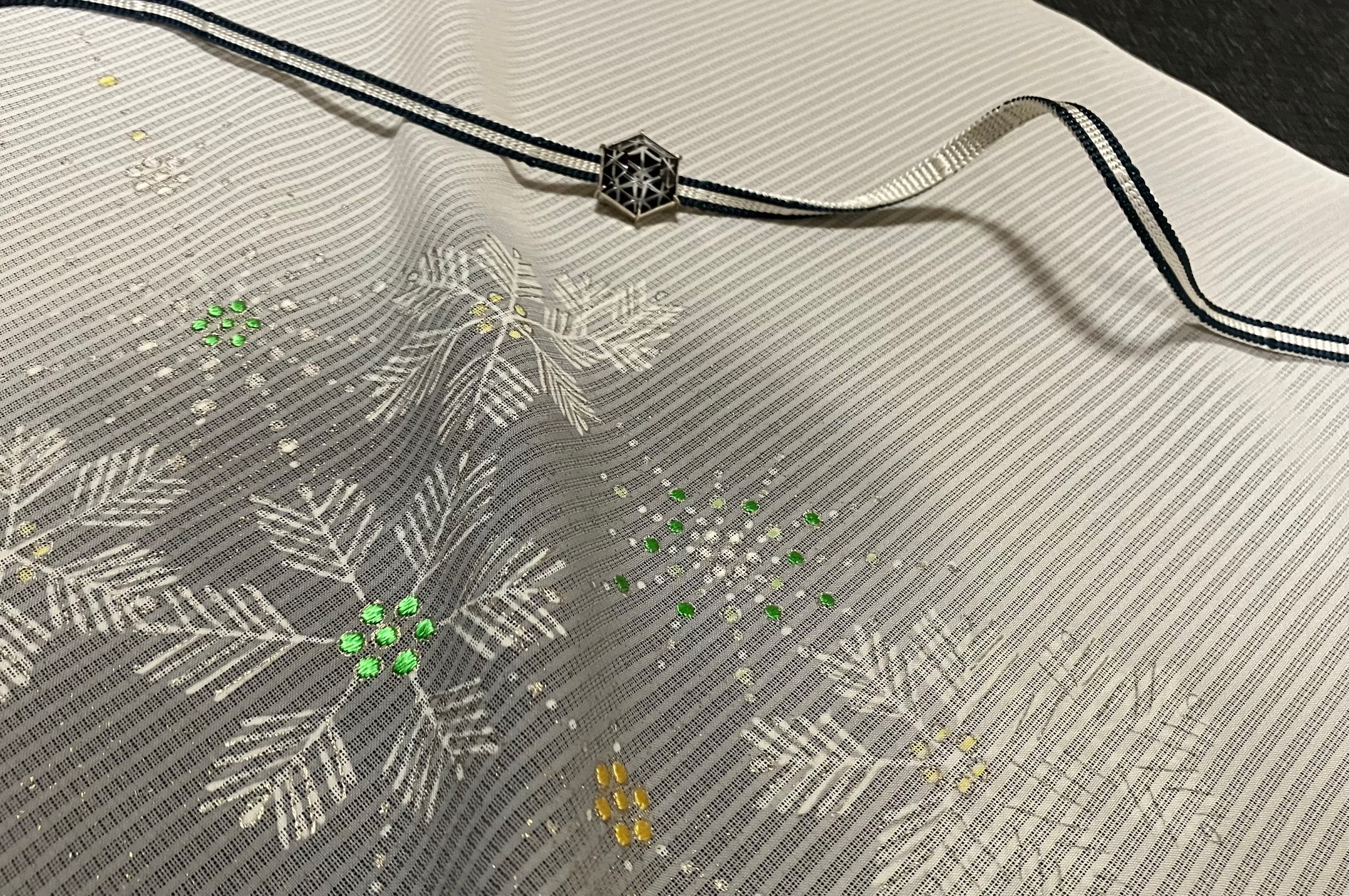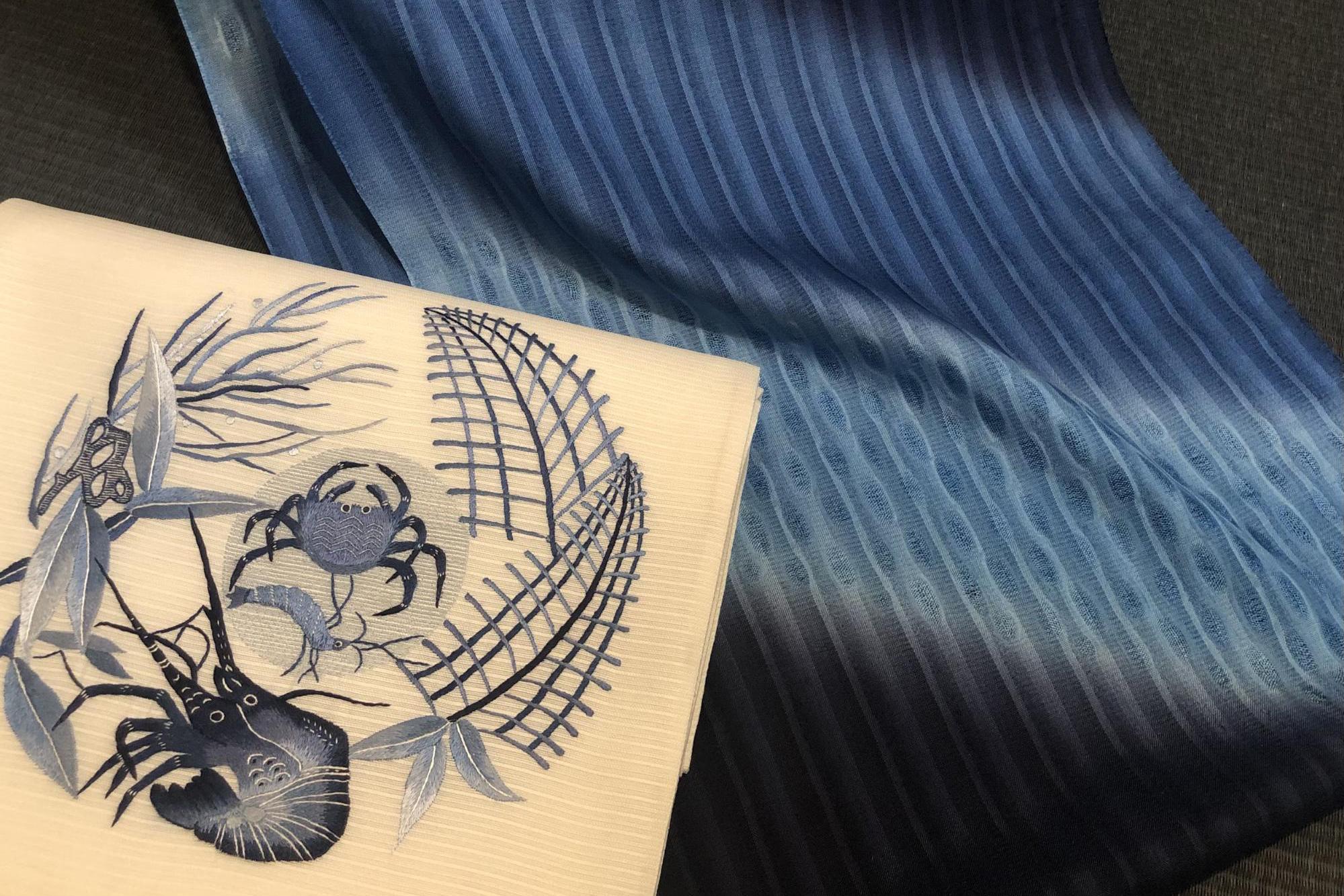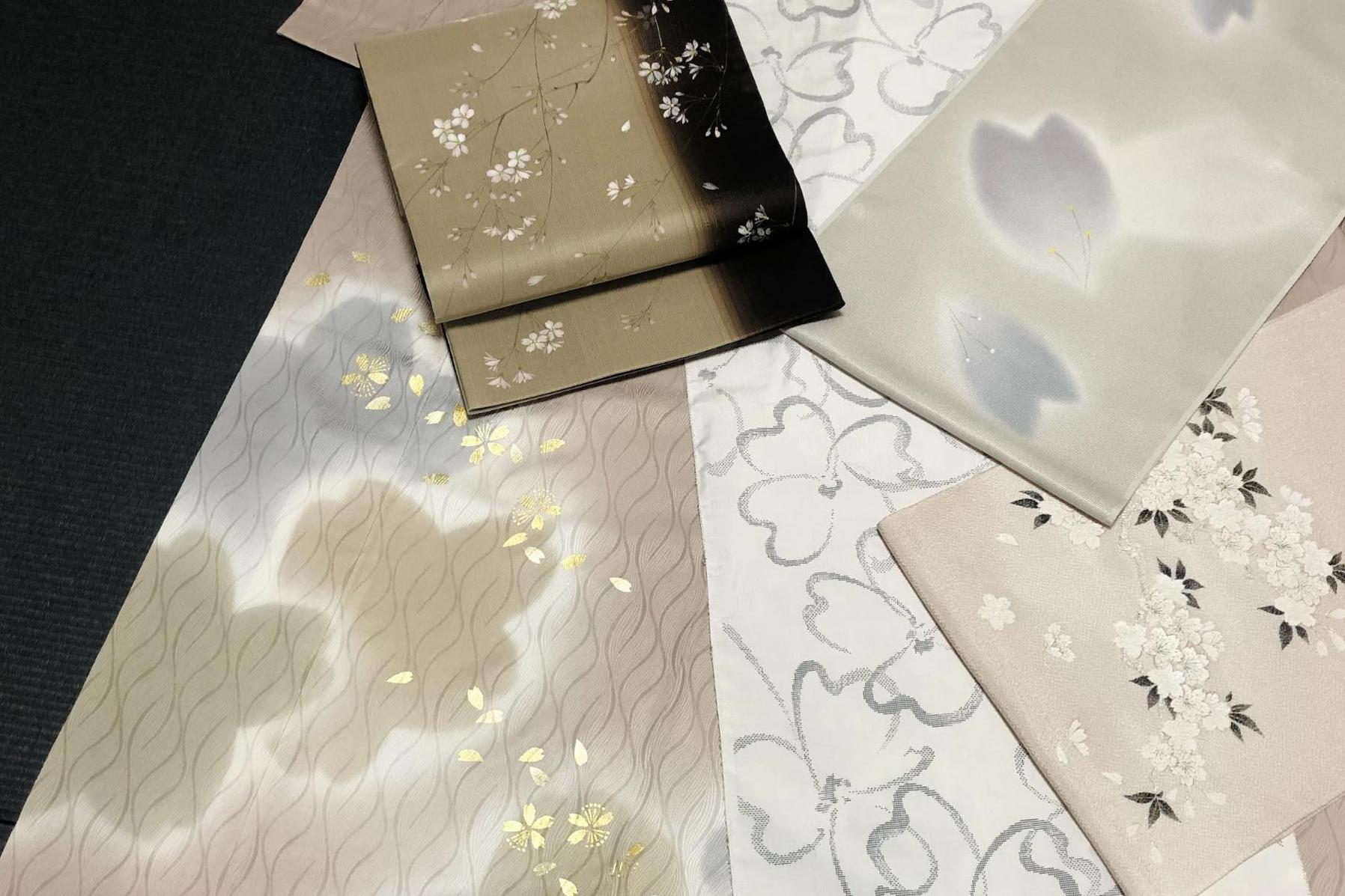夏の祝言 〜小説の中の着物〜 平岩弓枝『御宿かわせみ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十三夜
小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は『御宿かわせみ15 恋文心中』より「祝言」。現代ではまず見ることのできない、夏の婚礼衣裳のお話。
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2024.04.08
連載記事
日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜
-

2024.03.12
連載記事
節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜
-

2024.02.02
連載記事
美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜
-

2023.12.28
連載記事
徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜
-

2023.12.03
連載記事
働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜
-

2023.11.07
連載記事
“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜
-

2023.10.05
連載記事
掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜
-

2023.08.29
連載記事
愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜
-

2023.07.29
連載記事
雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜
-

2023.07.05
連載記事
羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜
-

2023.06.01
連載記事
宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜
-

2023.04.30
連載記事
女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜
-

2023.03.31
連載記事
蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜
-

2023.03.15
連載記事
滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜
-

2023.02.01
連載記事
“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜
-

2022.12.30
連載記事
“流れる”ような身のこなし 〜小説の中の着物〜 幸田文『流れる』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十夜
-

2022.12.26
連載記事
袖についての、ちょっとした考察 〜小説の中の着物〜 河治和香『国芳一門浮世絵草紙3ー鬼振袖ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十九夜
-

2022.11.05
連載記事
インスピレーションソース 〜小説の中の着物〜 北原亞以子『慶次郎縁側日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十八夜
-

2022.10.31
連載記事
ほのかにまとう雅の薫り 〜小説の中の着物〜 諸田玲子『王朝まやかし草紙』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十七夜
-

2022.08.29
連載記事
生かしきる、ということ 〜小説の中の着物〜 中島要『着物始末暦シリーズ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十六夜
-

2022.08.15
連載記事
創る悦び、着る悦び 〜小説の中の着物〜 乙川優三郎『夜の小紋』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十五夜
-

2022.07.27
連載記事
かくも凄まじき芸の道 〜小説の中の着物〜 有吉佐和子『連舞・乱舞』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十四夜
-

2022.07.27
連載記事
夏の祝言 〜小説の中の着物〜 平岩弓枝『御宿かわせみ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十三夜
-

2022.04.27
連載記事
”品”と”説得力”、そして”スタイル”「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十二夜
-

2022.05.11
連載記事
先取り単衣と染め帯の愉しみ 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十一夜
-

2023.03.01
連載記事
そろそろ桜も 〜現代フォーマル着物考その2〜「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十夜
-

2023.03.27
連載記事
ちょっと、きちんと 〜現代フォーマル着物考その1〜「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第九夜
-

2022.12.20
連載記事
めでた尽くしで、歳神さまをお出迎え 〜モチーフで遊ぶ〜 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第八夜
-

2022.12.03
連載記事
秘めつつもこぼれ出るものに人は惹かれる「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第七夜
-

2021.11.23
連載記事
ちらり、秘かな愉しみ 〜裏とか紋とか〜 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第六夜
LATEST最新記事
RANKINGランキング
-

まなぶ
半衿(はんえり)とは?着物との組み合わせ方・選び方や縫い付け方法まで解説
-

まなぶ
名古屋帯とは?袋帯との違いと種類ごとの使い分け・最適な仕立て方まで解説
-

まなぶ
肌襦袢(はだじゅばん)とは?長襦袢との違いは何?
-

まなぶ
着物の種類と、初めての着物を「付け下げ」にするべき5つの理由
-

まなぶ
留袖とは?結婚式などフォーマルな場での黒留袖の着用マナーと柄の選び方
-

まなぶ
小紋・江戸小紋とは?柄の種類や選び方【着物の種類 基本中のき!カジュアル編②】
-

まなぶ
着物の下着は何を着ればいい?おすすめのブラ・ショーツ・下着を紹介!
-

まなぶ
「訪問着」を徹底攻略!~6つのお悩み実例・解決いたします〜
-

まなぶ
辻が花とは?幻と称される染め物の特徴をご紹介
-

まなぶ
袋帯の多様な種類 丸帯・袋帯・洒落袋帯 シーンや着物に合わせたコーディネート解説